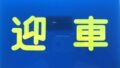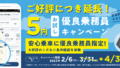とりま、今回はタクシー配車アプリ「GO」の連続配車モードについてks行と思います。以前の配車アプリでは1件ずつ配車を受ける形が基本でしたが、連続配車モードの登場により営業効率が大幅に向上しました。しかし、導入状況や運用方法は会社や地域によって差があります。
【かつての配車アプリ時代には連続配車モードは存在していなかった】
2020年頃までのタクシー配車アプリ「MOV」の時代は、乗務員は1件の配車を終えてから次の依頼を待つ必要がありました。そのため、営業効率には課題がありました。後に「MOV」と「JapanTaxi」が統合され、「GO」として新たな配車サービスが開始され、効率的な配車を目指して順次連続配車モードが導入されました。しかし、導入時期やリリース時期は公式に公開されておらず、会社や地域によって差があります。
【連続配車モードは配車間の空白時間を減らす仕組みになっている】
連続配車モードでは、1件の配車を終えたあとにアプリ上で「了解」ボタンを押すだけで、次の配車が自動的に割り当てられます。これにより配車間の空白時間が減り、効率的な営業が可能になります。ただし、手挙げの客を誤って乗せてしまうリスクを防ぐため、配車中はスーパーサインを「回送」に切り替える運用が多くの事業者で推奨されています。表示灯の切り替えは乗務員の手動操作であり、GOのシステムが自動で切り替えるわけではありません。
【以前は迎車専用アカウントが必要だったが現在は通常アカウントで対応可能】
連続配車モードが普及する以前は、「迎車専用アカウント」を用いて流し営業をせず配車アプリからの迎車依頼のみを受ける運用が広く行われていました。この方法は効率化には役立つものの、ログインや操作の複雑さが課題でした。現在では、GOアプリの機能向上により通常アカウント内で連続配車モードを切り替えて使用可能になり、迎車専用アカウントはほとんど廃止されています。
【連続配車モードの導入状況は会社や地域によって異なる】
連続配車モードはすべてのタクシー会社で利用できるわけではありません。大手グループや無線配車を主軸とする会社では導入が進んでいる一方、中小や個人タクシーでは未対応のケースも多くあります。横浜エリアでも一部の会社で導入されており、効率化に役立てられていますが、全社対応ではありません。GOアプリ自体は横浜全域で利用可能ですが、連続配車モードや配車スコアによる優遇などの活用度は事業者によって差があります。
【纏め】
連続配車モードはタクシー業界の営業効率化とサービス向上を目指す仕組みですが、導入や運用には会社や地域ごとに差があります。乗務員は配車効率を上げつつ、手挙げ客との兼ね合いを考えた運用が求められます。今後は、さらに普及や運用改善が期待される分野です。