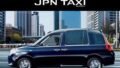今回は「距離時間併用運賃と深夜割増」について、ゆる〜くまとめてみます。(笑)(*´ω`)
【距離時間併用運賃っていつから?】
今では当たり前の 距離時間併用運賃、実は昭和45年(1970年)に導入されていて、なんと 54年前 から続いている制度です。
導入の理由は、渋滞や信号待ちの間、従来は運賃が発生せず、乗務員が不利益を被ったり、乗車拒否が起きたりしたため。
つまり「渋滞でも信号待ちでもちゃんと運賃がもらえるようにしましょう」ということですね。
【昭和45年の運賃って?】
東京での料金は、
- 初乗り:1.5kmで130円
- 加算:1kmごとに50円
今と比べると…なかなか笑えます。ちなみに昭和45年のタバコの値段は、
- ハイライト:70円 → 現在520円(約7.4倍)
- セブンスター:100円 → 現在600円(約6倍)
タクシーの初乗りは今の500円÷当時の90円≒5.5倍、加算料金は今の100円÷当時の12.5円≒8倍。
…なんか比べる意味がよく分からないけど(笑)、ざっくり物価感の参考にはなるかもです。
【高速道路と距離時間併用運賃】
日本の高速道路は、
- 名神高速:1963年7月開通
- 東名高速:1969年全線開通
- 首都高速:1962年一部開通、C1全線1967年、C2全線2015年
当初、高速道路利用時の運賃は距離だけの計算だと不公平との指摘がありました。そのため、距離時間併用運賃が高速道路では一部適用除外となったのは 昭和55年(1980年) です。
【深夜割増っていつから?】
深夜割増料金は昭和29年(1951年)に導入。
目的は、深夜帯のタクシー運行にかかる追加コストや乗務員の労働条件改善のためです。
当初は 20%増し、その後1981年(昭和56年)に30%にアップ、さらに1987年(昭和62年)に再び 20% に引き下げられ、現在に至ります。
【纏め】
距離時間併用運賃も深夜割増も、実は意外と歴史が古く、昭和の頃から「乗務員の不利益を減らすため」に工夫されてきた制度。
今では当たり前すぎて意識しない人も多いですが、渋滞や深夜でも安心して利用できる背景には、長年の制度設計があるんですね。
今回はただの知りたがり話でした(笑)\(^o^)/