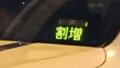今回は「距離時間併用運賃と深夜割増の歴史と現在」について解説します。
距離時間併用運賃は渋滞や信号待ちでも運賃が発生する仕組みで、深夜割増は夜間の追加コストに対応する仕組みです。両制度は長い歴史を持ち、現在のタクシー運賃にも大きな影響を与えています。
【距離時間併用運賃の誕生は54年前】
距離時間併用運賃は昭和45年(1970年)に導入されました。当時は渋滞や信号待ちで運賃が発生せず、乗務員が不利益を被ることが多かったためです。
この制度により、渋滞時でも公平な運賃が確保されるようになりました。
【昭和47年の東京タクシー料金】
1972年(昭和47年)の東京では、初乗り1.5kmで130円、加算は1kmごとに50円でした。
参考までに、当時のタバコの価格は以下の通りです:
- ハイライト:70円
- セブンスター:100円
現在の初乗り500円と比較すると、タクシー料金は約5.5倍に上昇しています。
【加算単価の変化】
当時の1mあたりの加算単価は0.05円/m。
現在の255m加算で100円と比べると、約8倍の水準です。
長期的に見れば、タクシー料金はタバコよりも上昇幅が大きいことがわかります。
【高速道路と距離時間併用運賃】
日本の高速道路は1963年(昭和38年)に名神高速が開通。
高速道路利用時の運賃計算は、距離時間併用運賃導入前は不公平が指摘され、1980年(昭和55年)に適用除外となりました。
【深夜割増の歴史】
深夜割増は1951年(昭和29年)に導入されました。
当初は20%増しで、夜間の追加コストと乗務員の労働条件改善を目的としていました。
その後1981年(昭和56年)に30%に引き上げられ、1987年(昭和62年)に再び20%に戻されています。
【まとめ】
- 距離時間併用運賃は1970年から導入され、渋滞や信号待ちの不公平を是正
- 深夜割増は1951年に開始、現在も20%増しで運用
- 初乗り・加算単価は長期的に大きく上昇している
- 高速道路利用時は1980年に距離時間併用運賃の適用除外
距離と時間を考慮した運賃制度は、タクシーの公正な料金体系を支え続けています。