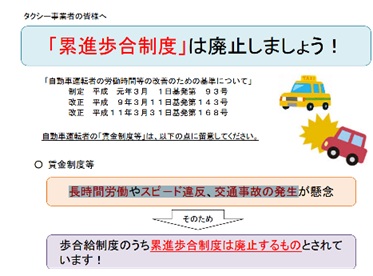今回は「累進歩合が『悪者』にされた結果、なぜか生活はもっと苦しくなった件」を書こうと思います。
とりま、タクシー業界でよく使われてきた「累進歩合制」は、たしかに働けば働くほど稼げる仕組みです。その一方で、長時間労働やスピード違反、事故のリスクを高めるとして、国の「改善基準告示」では、あまりよろしくない制度とされ、指導対象になることもあります。
そこで最近では、「積算歩合制=定率歩合」が「安全で健全な働き方」として推奨されるようになりました。あらかじめ段階的に営収に対して一定の歩合率を決めておくことで、無理な稼ぎ方を防ぎ、労働時間を短縮しようという意図です。
ですが、この制度、現場では「給料が下がった」、「もっと働かないと生活できない」といった声が相次いでいるようです。
累進歩合をやめたことで、労働環境は良くなるどころか、逆に生活が苦しくなった人も多い様です。
今回はそんな「良かれと思ってやった結果、むしろ悪化した」制度の実態にを書こうと思います。
【建前では累進歩合は「危ない制度」?】
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準についての改善基準告示」では、累進歩合について次のように記されています。
累進歩合制は、労働時間の延長や競争的な運転行動を助長し、スピード違反や交通事故等の発生を招くおそれがあると。
つまり、「頑張れば頑張るほど稼げる」仕組みが、ドライバーを危険な働き方に追い込んでしまう、というわけです。
そのため、代わりに推奨されるのが「積算歩合制=―定率歩合制)」で、営収に対して段階的に一定の率で報酬を支払うことで、無理して走っても稼ぎは変わらない=安全運転を促すという考え方です。
制度の意図としては、非常にごもっともですが・・・・
【現実で積算歩合になったら、手取りが減った?】
この積算歩合の仕組みは「安全寄り」なのかが疑問ですが、会社側が導入する際に歩合率を下げてしまうケースが後を絶ちません。
たとえば、月に50万円の営業収入をあげたとして、歩率60%の累進歩合時代には30万円以上もらえていたのに、積算歩合にした途端、20万円台まで下がってしまった・・・・そんな話は珍しくありません。
結果として、乗務員の多くはこう思います。
「今まで通りじゃ生活できないから、もっと走らなきゃ」・・・・・
…あれ?
長時間労働や無理な運転を防ぐために累進歩合をやめたのでは?(笑)
結局のところ、「給料が減るなら、稼ぐしかない」→長時間労働に逆戻りという悪循環が生まれてしまうのです。(笑)
【結論、制度は安全でも、生活が成り立たない】
改善基準告示は、「労働時間の短縮」や「安全運転の推進」を目的とした制度です。ですが、その一方で「生活できる水準の収入をどう確保するか」という視点が抜け落ちています。草
制度の意図がどれだけ正しくても、乗務員の生活が立ち行かなくなっては本末転倒です。
累進歩合のような「頑張れば報われる」仕組みを排除した結果、「頑張っても報われない」構造に陥っているとすれば、それはもう制度と現実がまったく噛み合っていない証拠です。
【誰のための制度?】
「長時間労働を防ぐために、歩合を下げましょう」
・・・・という理屈が、現場では「生活できないなら、もっと走るしかない」、「結局、以前より働くことになった」
という現実を生んでいます。
制度の理想と、現場の実情。その間に横たわるギャップを埋めない限り、どんなに安全な仕組みを導入しても、それを使う人の生活は守れないままです。
【累進歩合が危険とされるけど、科学的根拠はあるの?】
改善基準告示では累進歩合制について、「長時間労働やスピード違反、交通事故の発生が懸念される」と明記されています。つまり「稼げば稼ぐほど働き過ぎて事故も起こしやすいですよ」と警告しているわけです。
ですが、ここで気になるのは、その懸念にはちゃんとした科学的根拠があるのでしょうか?
残念ながら、現時点で「累進歩合があるから事故が増える」、「スピード違反が増える」と明確に統計データや実験結果で証明された資料は、公開されていません。
行政や労働基準監督署が指摘するのは、あくまで「理論的にそうなる可能性がある」という「懸念」レベルの話であり、「確実にそうです」と証明されたわけではないのです。
つまり、「累進歩合=悪者」という評価は、どこか「話が先走っている」感も否めません。
現場の乗務員や業界関係者の中には「働き方や賃金体系は単純な原因・結果では語れない」という声も多いのが実情の様です。
【ではなぜ警告されるのか?】
なぜそれでも改善基準告示が累進歩合を危険視しているかと言うと、「歩合率が上がるほど無理して稼ごうとする意欲が高まりやすい」という、労働動機に関する心理的な推論に基づいているからです。
つまり「人間の心理として、稼げるなら時間や安全を犠牲にしてしまうかもしれない」という、可能性を予防的に警告しているわけです。
これを科学的根拠と呼ぶには物足りなさがありますが、安全第一の観点から行政が慎重になるのは理解できます。
【なぜ法律で禁止しないのか?・・・規制のグレーゾーン草】
改善基準告示では累進歩合制を「望ましくない」と位置づけていますが、法律で禁止されていないのはなぜでしょう??。
その主な理由は以下の通りだと思います。
1. 累進歩合は賃金制度の一種であり、直接の違法性が認められていない
累進歩合は「働いた分だけ稼げる」という賃金形態の一つであり、労働基準法は賃金の最低限の保障を目的としているため、賃金の計算方法まで細かく規制する法律はありません。
そのため、「違法」と断じるためには明確な法的根拠が必要ですが、累進歩合自体はそれに該当しません。
2. 運用次第で問題が起きるが、制度自体は多様性を認められている
労働環境や業務内容は多様であり、一律に累進歩合を禁止してしまうと、乗務員の自由な働き方や収入アップの機会を奪う恐れもあります。
つまり、行政も「制度そのものがダメ」というよりは、「長時間労働や違法運転を招かない運用が大事」としている訳です。
3. 禁止すると監督指導の効果が薄くなる懸念
改善基準告示はあくまで「指導の基準」でなので、現場で違反があった場合に是正指導をしやすくする役割も担っています。つまり、もし法律で禁止してしまうと、事例ごとに裁判や行政処分に発展しやすく、現場での柔軟な対応や合意形成が難しくなるリスクもあります。
【要は・・・】
「改善基準告示」という行政ルールで注意喚起しつつ、現場の運用や企業の自主的な対応に任せているのが現状で、累進歩合の問題点を法律で一律禁止するには、社会的な議論や国会での法改正のプロセスが必要であり、現時点ではそこまで踏み込めていないのが実情と言えます。
【まとめると】
ポイント 実情
累進歩合と事故や違反の因果関係 科学的な統計データやエビデンスは公開されていない
改善基準告示の立場 心理的推論に基づく“懸念”を元に指導・推奨している
現場の声 歩合制度より労務管理や環境整備の方が重要との意見多数
このように、累進歩合を危険視する改善基準告示の主張は、どう見ても「科学的根拠ありき」ではなく、「安全に配慮した予防的見解」であることを理解したうえで、実態と照らし合わせることが大切だと感じます。実際、積算歩合では累進歩合より同じ営収でも給料が下がるので、より、稼げるなら時間や安全を犠牲にしてしまうかもしれません。
【最後に】
本当に守られるべきは、「制度の正しさ」ではなく、「そこにいる人の暮らし」で、制度だけが先に走って、乗務員が追いつけないようでは、また別の形で危険が生まれるのではないでしょうか?。・・・・知らんけど(笑) (*