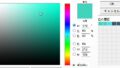今回は「山手通りと明治通り」について書こうと思います。
とりま、横浜の乗務員が「東京の道」と聞いてまず思い浮かぶのが、この2本なんですよね。・・・・いや、自分だけかもですが(笑)
横浜の乗務員が東京の道路について語るなんてお門違いって言われればそれまでですが、そこは大目に見てください (^_-)-☆
【山手通り】
まずは山手通り。
全長およそ19km、品川区から板橋区までを縦断し、目黒・渋谷・中野・豊島など都内のど真ん中を通っています。
都市幹線道路の中でも屈指の交通量を誇っていて、信号の数もハンパない。
普通、幹線道路って1kmあたり10〜20基の信号があるって言われますが、山手通りは体感的にもっと多いようです。
調べてみたらおよそ1kmあたり16基、全部で300基前後あるらしいんです。
T字交差点や十字路はもちろん、歩行者専用やわき道の入口まで信号だらけ。運転していると「また赤かい!」ってツッコミ入れたくなります(笑)
【明治通り】
一方の明治通り。
東京都道305号として知られていて、港区から北区まで約23kmを貫いています。新宿・渋谷・池袋といった主要エリアを突っ切るので、人も車も常にいっぱい。
こちらも信号だらけで、推定230〜460基!平均すると約345基くらい。1kmあたり15基という計算で、山手通りといい勝負ですね。
【信号が多いとどうなる?】
もちろん都市部の安全確保や交通整理のためには信号は欠かせません。
ただドライバー目線では、これが「小刻みに止められる要因」にもなってるんですよね。
特にタクシーだと、停車の積み重ねが加算料金につながります。
最近はキャッシュレス決済が増えて「ピッ」で済むからこそ、100円単位でチクチク上がっていく運賃が気になる…。
で、ふと考えると「あぁ、信号の多さがそのまま可視化されてるんだな」と実感します。
【まとめ】
山手通りも明治通りも、都心の大動脈。
信号機の数は「ちょっと多すぎじゃない?」と思えるくらい設置されていて、それが都市の交通の安全と効率を両立させている…はずなんですが、運転してる側からすると「いやいや、運賃上がるやん!」ってボヤきたくもなります(笑)
都市を走るだけでは見えないけれど、信号の数を意識してみると、街の仕組みや交通事情がちょっと違った角度から見えてきますよ。
…って、また真面目モードになってしまいました。真面目か?パート2(笑)