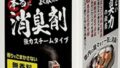今回は「全国で進をむタクシー運賃値上げラッシュ・・・・・陸運局が握る「要否判定」と損益分岐点の舞台裏」を書こうとおもいます。
とりま、日課にしているネットのパトロールをしていると(笑)、ここ最近、全国で一斉にタクシー運賃の値上げが相次いでいます。新聞やネットで「値上げ決定」の見出しを目にするたびに、「本当に会社の経営がそんなに苦しいのか?」と疑問に思う人もいるはず。数字で見ると、その背景がもっと素直に見えてきます。
申請したからといって即「値上げ決定!」とならないのがこの業界の特徴です。・・・・どうして審査がすぐ始まらないのか?それには陸運局が行う「要否判定」というプロセスが関係してる様です。
【値上げ申請=すぐ審査開始じゃないワケ】
タクシーの運賃改定は国の許可が必要な認可制。申請は各事業者が陸運局に提出しますが、その内容を即座に審査に回すわけではありません。
まず陸運局は、申請書類だけでなく、会社の経営状況や帳簿類を提出させ、申請が妥当かどうか「要否判定」を行います。
この段階はまさに「そもそも本当に値上げが必要なのか?」を見極めるための予備審査であり、全申請の中から本格審査に進む案件を絞り込んでいるのです。
【損益分岐点がカギ】
値上げの要否判定でよく使われるのが「損益分岐点売上高」の計算です。これはざっくり言うと、「この売上がなければ赤字になる」というラインのことを指します。
例えば、売上が7,500万円のタクシー会社があるとします。
主に乗務員の歩合給などの変動費=売上の60%
固定費=事務職・役職給与、車両費、保険料など=100-60=売上の40%とすると
このとき損益分岐点は、損益分岐点売上高=固定費÷(1−変動費率)=3,000,000÷(1-0.6)⁼75,000,000円
実はこの例では、損益分岐点売上高=実際の売上とぴったり同じで、つまり利益はゼロになります。
【どういうこと?】
つまり、この会社は今の売上でようやくトントン。
もし燃料費が上がったり、固定費が増えたり、売上が少しでも減ると赤字になってしまう、非常にシビアな状況の会社です。
こんな状況だと、値上げの申請は陸運局からも「認めざるを得ない」と判断されやすくなります。
【だから申請だけで即審査にはならない】
しかし、「値上げ申請があった!」=「即審査スタート」ではありません。
陸運局はこの計算式や経営状況、帳簿、将来の支出見込みなどを総合的に判断し、「本当に値上げを認めるべきか?」を慎重に検討するための時間を取っています。
この「要否判定」を経て、審査が必要と判断された申請だけが次のステップへ進みます。
【黒字でも値上げが通ることがある理由】
今まではギリの会社でしたが黒字の会社はどうなる?と思います。損益分岐点や利益の計算を見ると、「黒字なら値上げは不要なのでは?」と思うかもしれません。
確かに単純に帳簿上で利益が出ている会社もありますが、それでも値上げ申請が認められるケースは決して珍しくないようです。
なぜなら、黒字かどうかだけで判断できない以下の様な複雑な事情があるからです。
1. 利益率が極端に低い場合
売上が大きくても、利益率が1〜2%程度など非常に低いと、少しのコスト増(燃料高騰、人件費上昇、保険料増など)であっという間に赤字に転落します。
こうした「ギリギリの黒字」は経営の安定性が非常に脆弱で、陸運局は将来のリスクを考慮し値上げを認めることがあります。
2. 今後避けられないコスト増が見込まれる場合
例えば、車両の大規模な更新が必要であったり、法改正に伴う保険料の上昇など、経営者が今後避けられない支出増を予測している場合。
現状黒字でも、この将来的負担を見越して運賃改定を申請し、認められることがあります。
3. 区域全体のバランスを考慮する場合
同じエリアの複数の会社が値上げを申請し、区域全体で運賃水準の引き上げが求められているケ
ースもあります。
黒字企業であっても、この区域の総合的な事情を踏まえ、運賃改定が認められることがあります。
【まとめ】
全国でタクシーの値上げ申請が増えていますが、審査はすぐ始まらなく、陸運局は会社の経営状況を帳簿などで細かくチェックし、「要否判定」を行います。
赤字か黒字かギリかどうかだけで値上げ申請が認められるかは決まりません。
重要なのは「経営の安定性」や「将来の見通し」、「区域全体のバランス」など複数の要素です。
だからこそ、陸運局は帳簿や計画書を詳しくチェックし、申請が正当かどうかを見極めているのです。
と入っても損益分岐点売上高の計算が重要で、売上がその水準に近いかどうかがポイントになり、実際の売上と損益分岐点がほぼ同じ場合は値上げ認可されやすく、申請は「見せかけ」ではなく、数字で裏付けられた本当に必要な値上げかどうかが問われています。
タクシー料金が上がるニュースの裏側には、こうした地道で複雑な計算と判断があるのです。