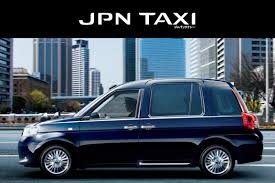最近、タクシーやライドシェアで話題の「時間変動制運賃」、いわゆるダイナミックプライシング。雨の日や通勤ラッシュなど需要が多い時間帯は料金が上がり、逆に需要の少ない時間は下がる仕組みです。政府も規制改革の一環として検討を進めていますが、果たして現場や利用者にはどのような影響があるのでしょうか。今回は、アメリカのライドシェア事例も交えながら日本の状況を読み解きます。
【時間変動制運賃とは】
2021年1月、当時の規制改革担当相・河野太郎氏が、タクシー料金の規制緩和に意欲を示したことがきっかけで話題になりました。
内容は、タクシーやライドシェア利用者にとって「需要に応じて料金が変動する仕組み」です。
実証実験例:
- 2021年10~12月、ウーバーと日交が事前確定型変動運賃の実証実験を実施
- 変動幅:通常運賃の5割引き~5割増し
- 料金設定はタクシー事業者が自由に決定可能
【国交省の検討会も設置】
正式名称は長いですが(笑)、
「タクシー及び日本版ライドシェアにおける運賃・料金の多様化に関する検討会」が令和6年8月6日に立ち上げられ、現在までに3回開催。
目的は、タクシーと日本型ライドシェアの運賃制度をどうするかを検討することです。
しかし、現状では事前確定型変動運賃を導入しているタクシー会社はほぼ皆無。
実際に導入している会社を知っていたらぜひ教えて欲しいところです(笑)。
【アメリカの事例と日本の逆行】
アメリカではウーバーが事前確定型変動運賃を採用していますが、ライドシェア大手のリフトはダイナミックプライシングの弱点を認め、定額制を導入しています。
- 月額2.99ドル(約450円)で、需要が高い時でも料金高騰を回避可能
- 高需要時のサージプライシングを抑制
日本では検討会がダイナミックプライシング導入を議論中ですが、アメリカ本家のリフトは逆方向の料金制度を選択しているという皮肉な状況です。
【数字と現場のギャップ】
日本でダイナミックプライシングを導入するとすれば、変動幅は5割増減の範囲ですが、
現場の事情を考えると変動幅は小さくなる可能性大。
理由:ユーザーが高騰料金を嫌って避ける、タクシー会社も収益や効率を考慮するため。
結果として、日本型ライドシェアがタクシー料金を大幅に変動させれば:
- タクシーの利用者が奪われる
- 本来補完するはずのライドシェアが高額で敬遠される
という本末転倒現象も起こり得ます。
【今後の見通し】
- 2024年6月21日、規制改革実施計画で「需要と供給に応じた柔軟な運賃・料金」を検討と閣議決定
- 国交省の検討会も3回開催済み、論点整理段階
- 結論にはまだ至っていない
つまり、法律や検討会での議論は進んでいますが、現場では導入が現実化するかどうかは未知数。
数字だけ見れば「需要に応じた運賃」となるものの、実際には利用者やドライバーの動き次第で、仙台市ライドシェアのマッチング率96%のように、数字の上だけが先行する可能性もあります(笑)。
【まとめ】
- 時間変動制運賃=ダイナミックプライシングは、需要に応じて料金を変動させる仕組み
- 日本では規制改革実施計画や国交省検討会で議論中
- 実際に導入しているタクシー会社はほぼなし
- アメリカ本家リフトは逆に定額制を導入
- 現場の収益・効率やユーザー心理によって、実際の導入効果は不透明
結論:法律や計画でダイナミックプライシングが議論されても、現場ではまだ「絵に描いた餅」。数字だけ先行しても、現実は皮肉な結果になる可能性大です(笑)。