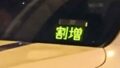横浜でタクシーに乗っていると、たまに思います。「東京って、信号多すぎじゃネ?」って。数百メートル進むごとに赤になって止まることもザラな様で、都心では「距離より信号の数で時間が決まる」と言われるほどだそうです。今回は、なぜ東京の道路はこんなに交差点が多いのかを、タクシー乗務員目線で見たいと思います。w
【東京都内の交差点、実はこんなにある】
国土交通省の「一般交通量調査」や各自治体の道路台帳調査では、「交差点密度(1kmあたりの交差点数)」という指標があります。
東京都内では平均して 1kmあたり10〜20個前後 の交差点が存在するとされています。都心部や住宅街など道路が細かく入り組んだエリアを含む統計的な平均ですが、実際には道路の種類や地域によって差があります。
【信号だけじゃない、多様な交差点】
交差点と言っても、信号のある大きな十字路だけじゃありません。
- 十字型交差点(+字型)
- T字型交差点
- Y字型交差点
- 歩行者専用信号付き横断歩道
- 信号なし・一時停止規制ありの小さな脇道からの出入口
つまり「交差点=信号機あり」ではなく、歩行者や自転車、側道からの合流点も含まれているわけです。
【都市計画と交通設計の影響】
千代田区や港区など都心部は、碁盤の目状の道路が基本で、1kmの直線区間に10〜15箇所以上の交差点が自然に発生します。
さらに「ゾーン30」などの生活道路安全対策で、わざと交差点を増やして車を減速させる施策も進んでいるため、交差点の密度が高まる一因になっています。
【社会環境の変化も影響】
新型コロナでキャッシュレス決済が普及したことも影響大。以前は乗客が小銭を出したり、釣り銭を用意したりで減速することがありましたが、今はほぼ信号や交差点でしか止まりません。
また、タクシーの初乗りや加算料金が100円単位に改定されたことで、短距離でも信号の数や交差点が「コスト感覚」に直結するようになったのも面白いところですw
【イライラも安全のため】
東京の交差点が多い理由は、都市構造・交通設計・社会環境の変化が複雑に絡んでいます。信号でイライラすることもあるかもしれませんが、それは同時に「安全確保」と「街の機能維持」のための仕組みでもあるわけです。
たまには道路を「次は何個交差点を越えるかな?」という視点で眺めてみると、普段見過ごしていた都市の姿がちょっと面白く見えるかもしれませんネ。(^_-)-☆